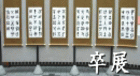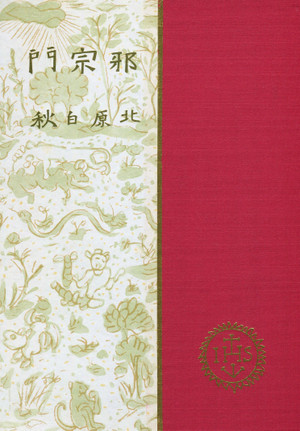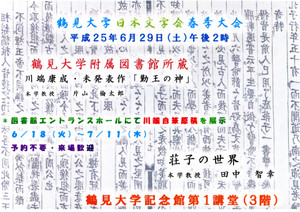2013年8月 7日 (水)
2013年7月29日 (月)
をのが影追ふ
8月4日(日)はオープンキャンパスです。
模擬授業は、江戸時代中期の俳人で画家としても有名な、与謝蕪村の句と画についての話です。
ぜひ足をお運びください!
水色の美しいオオシオカラトンボです。
蜻蛉(とんぼ)は夏にも多くみられますが、文学においては古来から秋の季題です。
涼しげな姿が爽やかな秋の季節によく合っているからでしょうか。
行く水にをのが影追ふ蜻蛉(とんぼ)かな 千代女(『千代尼句集』)
この写真を撮ったときも、実際にはかなり暑かったのですが、トンボの姿は涼しそうでした。
千代女の句では「とんぼ」ですが、
白壁に蜻蛉過(よ)ぎる日影かな 召波(『春泥句集』)
のように、「とんぼう」と四音で詠まれることも多くあります。
鶴見大学文学部日本文学科
2013年7月22日 (月)
土用の丑
昨日は多くの方々にオープンキャンパスにお越しいただき、どうもありがとうございました。
さて、今日は土用の丑の日です。
鰻を食べる日として知られていますが、土用とは何でしょうか。
中国古代には、宇宙は「木・火・土・金・水」という五気で満ちており、あらゆるものは五気のはたらきによって生じるとする、五行説が行われました。
五行説では、季節、方角、色、人の道徳など、あらゆる事柄が木・火・土・金・水のいずれかに当てられ、季節の場合、「木」は春、「火」は夏、「金」は秋、「水」は冬に割り当てられます。
これでは「土」がありません。
そこで、それぞれの季節の終わり五分の一の日数にあたる18日分を削って、それを集めて「土」としました。
土用の丑の日とは、特に夏の土用の間にやってくる丑の日のことです。
丑の日は12日のサイクルでまわってきますので、18日の間に二回丑の日がくる年もあります。
今年がそうした年で、8月3日が「二の丑」となります。
丑の日に鰻を食べる習慣は、江戸時代の平賀源内や大田南畝の発案という説もありますがよくわかりません。
十分栄養をとって暑さに負けず、よい夏休みをお過ごしください。
鶴見大学文学部日本文学科
2013年7月17日 (水)
道のべの木槿
7月21日(日)はオープンキャンパスです。
模擬授業では、新沢典子先生による古代神話についての楽しい講義がきけます。
受験生のみなさま、ぜひいらしてください!お待ちしています。
早くも梅雨明けし、本格的な夏がやってきました。
上の写真は、公園で見かけた八重咲きの木槿(むくげ)です。
木槿は夏から秋にかけて咲きますが、俳諧では秋の季語です。
芭蕉が野ざらし紀行の旅で詠んだ「道のべの木槿は馬に食はれけり」も秋の句です。
和歌や連歌では木槿はあまり詠まれません。
「槿花一日の栄」の言葉があるように、朝に咲き夕べにはしぼむ花としてはかないイメージのある木槿ですが、江戸時代には盛んに栽培され、白・赤・紫、一重・八重など、多様な品種が生み出されました。
『丹青弌斑』という本の中の木槿の図。
こちらは白い花弁で奥が赤い、一重の木槿です。
鶴見大学文学部日本文学科
2013年7月 4日 (木)
2013年6月22日 (土)
久方ぶりの、「お気に入り」【研究室から】
今日は、梅雨の晴れ間。
風格ある文房具を取り出してみました。
清朝乾隆(1736~1795)ころの文人、孫阜昌が愛玩した古硯です。
(伝来その他、詳しいことは今回省略)
細部がうまく撮影できず、すみません。
実物は、なめらかで深みのある硯面が油煙墨にふさわしい。
悪筆の某も、ちょっと何か書いてみたくなります。
じっくり作行きを検分、「水を持て参れ」との仰せ。
硯面に数滴垂らし、鋒芒を指で確かめられ、一言「明初」。
恐ろしい眼力に感心しました。
皆様それぞれの「お気に入り」で、机辺を飾られてはいかが。
研究が画期的に進む、ことはないにせよ、気分がよくなることは請け合います。
鶴見大学文学部日本文学科
2013年6月11日 (火)
2013年6月 4日 (火)
2013年5月24日 (金)
2013年5月16日 (木)
学習アドバイザーのご案内【在学生のみなさんへ】
日ごとに緑が深くなります。
卒業論文の題目をどうするか・日々の課題・授業でよく理解できないこと・気になる本・レポートのまとめ方・・・
小さな疑問も放っておくと手に負えなくなります。
教員への質問は勿論大歓迎ですが、学習アドバイザーに相談してみては。
みなさんの先輩が親身に助言してくれるはずです。
染付に2色の餅をあしらいました。
皿は、伊万里ではなく波佐見(長崎県)焼です。
当代屈指の歴史学者黒板伸夫先生は、ご先祖をたどると波佐見皿山奉行。
(奥様は、これまた高名な歴史小説家永井路子先生)
と言うことを、教えてもらえるかもしれません。
今年は大学院生の山崎兼人君が担当します。
毎週木曜、午後3時から7時まで。
図書館メインカウンター脇へ、どうぞ。
鶴見大学文学部日本文学科