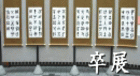鶴見日本文学会賞のお知らせ
四年生のみなさま
卒業論文の執筆、おつかれさまでした。
さて、みなさんが入学時に会員となっている鶴見大学日本文学会には、優秀な卒業論文を褒賞する制度があります。
受賞対象者は毎年六名程度、卒業証書授与式後に賞状及び賞品を授与いたします。
現在、自己推薦のエントリーを受付中ですので、我こそは!という方はぜひご応募ください。
エントリーの方法は、教学課、または日本文学科主任の片山先生から申請用紙を受け取り、卒業論文のコピーを添えて片山先生に提出してくださればOKです。
締め切りは平成二十六年二月十日、お待ちしております。
日光東照宮奥宮の鋳抜門の写真です。
奥宮は徳川家康の墓所で、有名な眠り猫の奥、長い石段を上がったところにあります。
こちらは二荒山神社。
東照宮が人でいっぱいだったのに対して、二荒山は意外なほど静かでした。
華厳の滝です。
麓にいるときには、山の方がこんなに雪とは想像していませんでした。
日光は高度によって気候がだいぶ違います。
鶴見大学文学部日本文学科