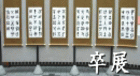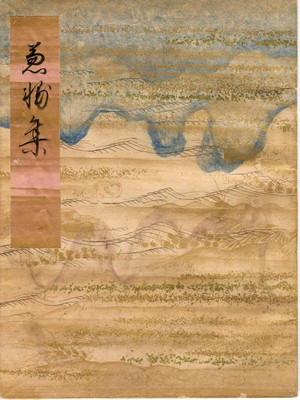2012年3月 1日 (木)
2012年2月14日 (火)
2012年2月 1日 (水)
ゆかり【研究室から】
と言っても、梅干しに使った紫蘇の加工品ではありません。
一昔前、ある先生のお手伝いをしましたら、「お礼に」と、くださったものです。
作られてから、もう半世紀近くたつでしょうか。
よく使い込んだ、銀の英国製筆記具です。
柔らかい光沢と流麗な彫刻、そして品格の髙さ。
優れた研究者であるのみならず、文章のうまさは群を抜いていらっしゃいました。
鋭い観察眼、皮肉の効いた言い回し、柔軟な表現、どれをとっても一流です。
惜しくも、先年なくなられました。
「ゆかり」のペンとシャープペンシルで先生の名文にあやかりたいと思うこと、切。
(なお、シャープペンシルは和製英語、米国ではメカニカルペンシル。さて英国では?)
2012年1月16日 (月)
2012年1月 5日 (木)
2011年12月23日 (金)
2011年12月11日 (日)
稀な機会【研究室から】
12月10日(土)、日本文学会秋季大会が催されました。
一般市民の皆様が多くいらっしゃったことは、驚きです。
後藤祥子先生のご講演は、犀利かつ自在。
和泉式部は1000年の後の知音に感謝しているでしょう。
岩佐美代子先生のご挨拶も、単なる挨拶の域を越える卓説のご披露でした。
また、その後の懇親会は楽しいお話の花盛りです。
学生・院生に卒業生、専任教員と他大学の研究者で賑わいました。
会が終われば、冬空に月食。
(古くは「ぐわつしよく」と読んでおります)
天体撮影の機材がありませんので、持ち合わせの道具を使いました。
不鮮明のところはご勘弁ください。
冴えた月食に出会うことは、稀かもしれません。
後藤・岩佐両先生のお話が一度に聞けたのは、もっと稀な、そして至福の機会です。