定期試験が終わり、ほっと一息、これから夏休みです。
(こちらは相変わらずの雑用と、後期授業の準備と、そして研究に追われています)
まとまった調べ物をしたり、長い小説を読んだり、旅行に出かけたり・・・
ともかくこの季節でないとできないことを、しっかりと。
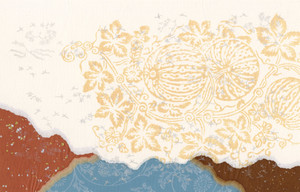
スイカのようにみえますが、大型のウリ(マクワウリ)でしょうか。
西本願寺本三十六人集の料紙を復元したものです。
スイカが日本にやってくるのは、南北朝の頃とか。
額田王や紫式部や源頼朝は、スイカを知らなかったのです!
季節の味も十分に堪能してください。