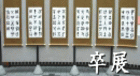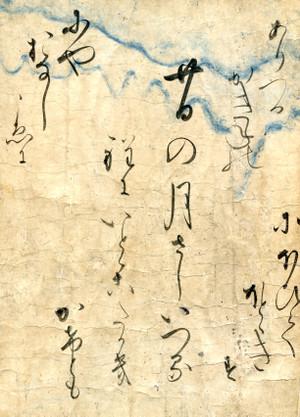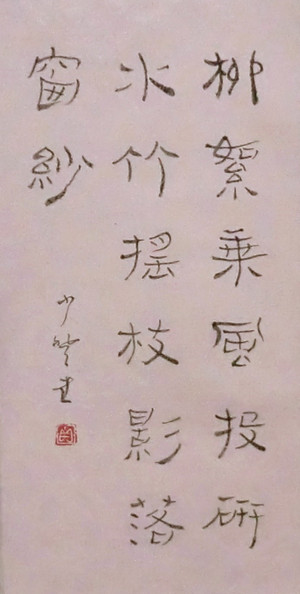源氏物語の五月【研究室から】
日一日と緑が濃くなる初夏のこの頃、いかがお過ごしでしょうか。
源氏物語には、5月を描いたところがいくつか出てきます。
よく知られているのは、やはり花散里の巻でしょうか。
「二十日の月、さしいづるほど」とありますので、ちょうど今頃です。
江戸の文人は巻の風情を「猶有杜鵑悲往事 橘花香処一声啼」と詠じました。
南北朝の抄出写本では、次のようになっています。
こんな本で読めば、また格別。
何で読んでも変わらないではないか、と仰る声が聞こえてきそうです。
もし、あなたが人も羨む大富豪でいらっしゃるならば、
少しくらい安手でしみったれた学問でも、まあよろしいでしょう。
しかし、一生遊んで暮らせるほどの資産をお持ちでなければ、
せめて学問くらい贅沢にしようではありませんか。
すてきな書物は、贅沢のひとつです。
さて、5月26日(日)は、オープンキャンパス。
午後1時より開催します。
図書館ではいろいろな貴重書を展示しますので、是非おいでください。
鶴見大学文学部日本文学科研究室