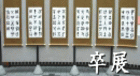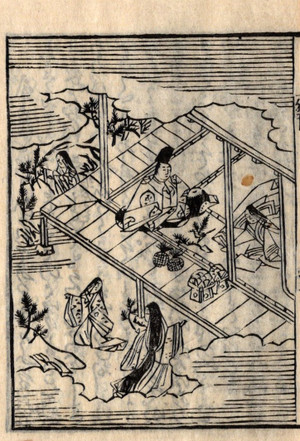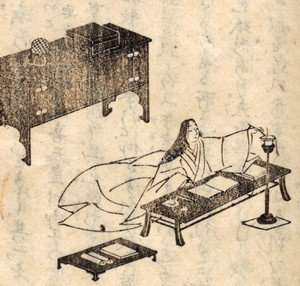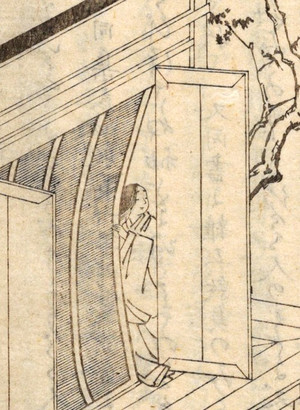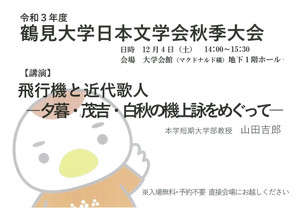春立てば【研究室から】
立春過ぎての雪となりました。
平安時代の和歌では、春になって降る雪が「残りの雪」です。
消え残っている雪ではありません。
(この話、以前記事にしました)
「春たてば花とや見らん白雪のかかれる枝にうぐひすのなく」
数ある古今集版本のうち、江戸時代に最も早く出版された本でご覧ください。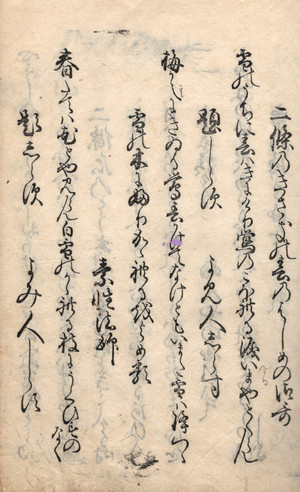 左から2行目、素性法師の歌です。
左から2行目、素性法師の歌です。
右から2行目「鶯のこほれる涙」が読めますか。
冬の寒さに鶯の涙さえ凍る、と言う着想のこまやかさ!
伝嵯峨本と呼ばれる、堂々の書物です。
同じ読むのであれば、贅沢な本。
本学図書館には、多くの古典籍があります。
展示や授業で実物に接することが出来るでしょう。
鶴見大学文学部日本文学科研究室