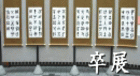有磯海
有磯海(ありそうみ)は富山の海岸で、古来歌枕として大変有名な土地です。
芭蕉は『おくのほそ道』の中で、有磯海を訪ねたいと思いつつ果たせなかった心残りを「わせの香や分け入る右は有磯海」の句に詠んでいます。
またこの辺りには、多祜の浦(たこのうら)という歌枕もあり、こちらは万葉の時代から藤が詠まれています。たとえば、次の越中の国守であった大伴家持の歌です。
藤波の影なす海の底清み沈著(しつ)く石をも珠とぞわが見る
(藤の花の影を作る湖の水が清いので、沈んでいる石も珠のように美しく見ることだ)
しかし、江戸時代には随分様子が異なっていたようで、安永七年に刊行された『おくのほそ道』の注釈書には「多祜の浦」について「海辺氷見の町の北、布施の海のほとり、今、田となる」と記されています。
この写真を撮った日には、海の向こうに雪をいただく立山連峰が見えました。
うまく写らず残念です。
鶴見大学文学部日本文学科