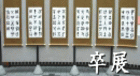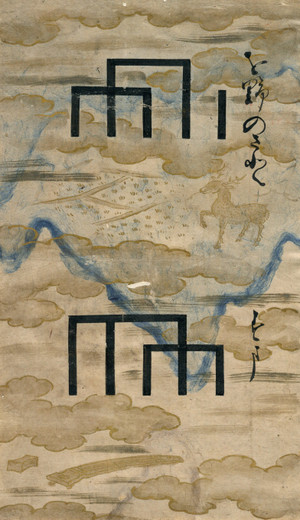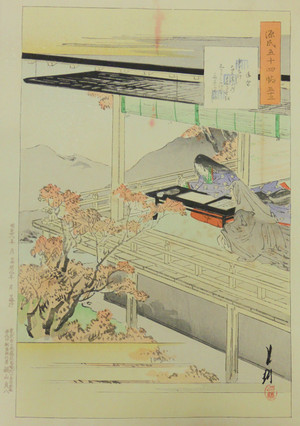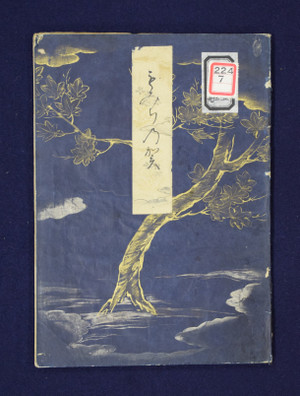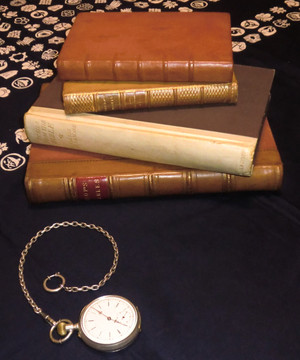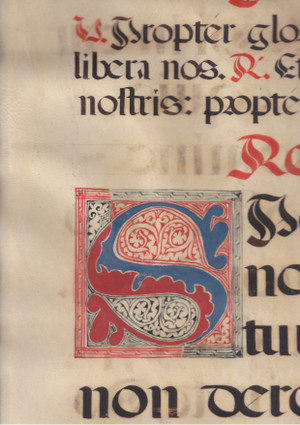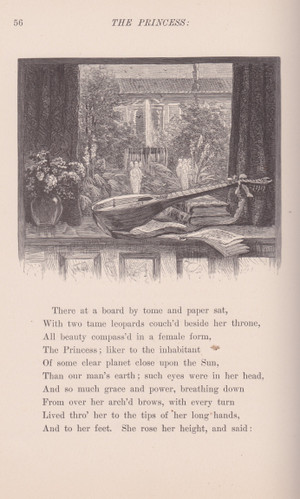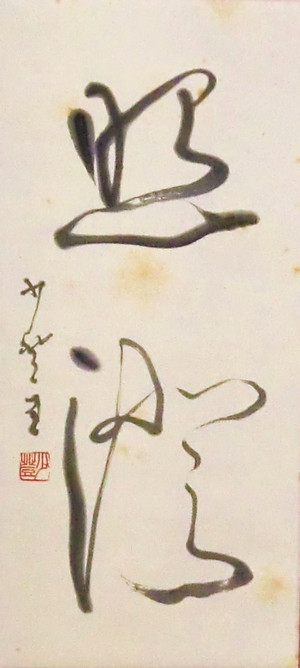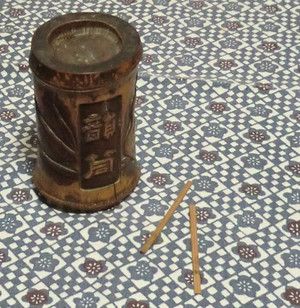奥の深い味【研究室から】
秋に収穫し、冬の間食べることの出来るものがいくつかあります。
(「秋収冬蔵」が思い浮かべば、上々)
栗は、そのひとつ。
記紀万葉の昔から好まれ、中国では詩経秦風に出てきます。
派手に舌へ響く味ではありません。
噛みしめれば、穏やかな甘さがじわりと伝わります。
(人も、かくの如き方を担当者は評価します)
源氏物語にも書かれていますので、お調べください。
江戸の昔は、丹波が名産地でした。
現在、品種が多様化し、あちこちで栽培されています。
加工品もさまざま。
到来物の栗蒸し羊羹にご登場願いました。
 羊羹には青磁、が漱石の鉄案です。しかし今回は青手九谷としました。
羊羹には青磁、が漱石の鉄案です。しかし今回は青手九谷としました。
小皿は、それほど古くありません(勿論、羊羹よりはうんと古い)。
さて、週末(30日)は、日本文学会秋季大会開催。
ご来場をお待ちしております。
鶴見大学文学部日本文学科研究室