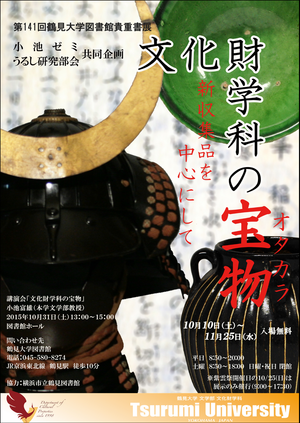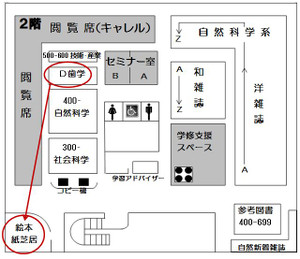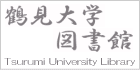明日が締め切りです!
明日9月30日は、選書ツアーの応募〆切です![]()
参加を希望している学生さんは急いで![]() 申込してくださいね
申込してくださいね![]()
![]()
今年度はこの1回しか実施しませんので、興味のある学生さんはぜひ参加してみてください![]()
![]()
![]() 学生選書ツアーとは
学生選書ツアーとは
図書館に入れて欲しい本を、書店に行って実際に見て選ぶツアーのことで、展示の際にはPOP作りなども手伝ってもらいます
![]() ツアー概要
ツアー概要
開催日時:平成27年10月15日(木)17:00~
開催場所:紀伊國屋書店 そごう横浜店7階
※交通費は自己負担です。
定 員:15名程度
特典:参加者全員に記念品プレゼント
![]() 申込方法
申込方法
「選書ツアー申込書」に必要事項を記入し、図書館メインカウンターへお持ちください。
申込資格:本学学生(POP作り、展示まで参加してくれる方)
申込締切:平成27年9月30日(水)
※ 「選書ツアー申込書」は図書館メインカウンターにあります。
※ 定員超過の場合、抽選になります(初めての方を優先します)。
![]() お問合せ先
お問合せ先
鶴見大学図書館 選書ツアー担当
TEL:045-580-8274 e-mail:sensho@tsurumi-u.ac.jp
たくさんの応募をお待ちしています(kt)![]()