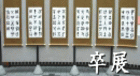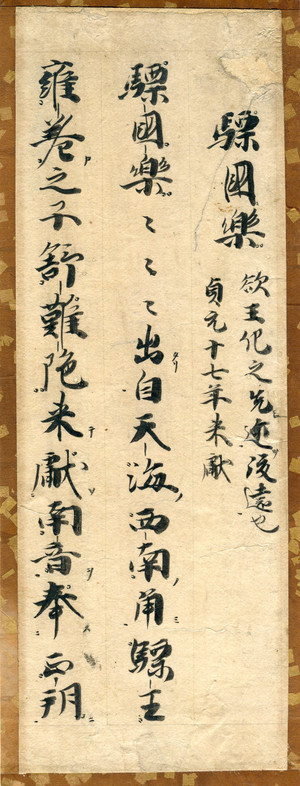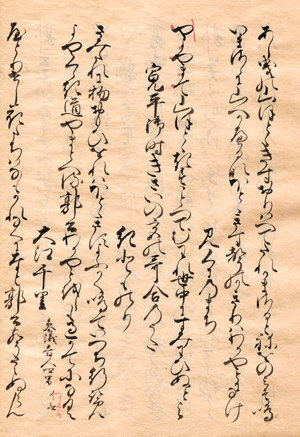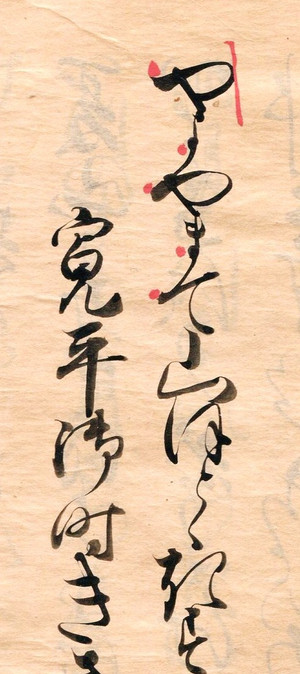2012年9月28日 (金)
2012年9月16日 (日)
2012年9月 6日 (木)
今昔【高校生・受験生のみなさんへ】
秋の風情が感じられるようになりました。
これからもうひとがんばり、の季節です。
ところで新しい建物が出来た時、ここに何があったのだろう、と思うことはありませんか。
ほんの少し前のことがわからなくなったり、あっという間に変わってしまったり・・・
100年ほど前、谷口香嶠(1864~1915)が描いた洛西長岡の秋です。
平城京の後、しばらく都がおかれました。
のどやかで、なんとなく古雅な風景が広がっています。
住宅地となった今からは、想像も出来ないほどの変化です。
さて、「のどやかで古雅な」文学を現代の情報機器に結びつけるとどうなるでしょう。
9月16日(日)のオープンキャンパスで、ちょっとお話しします。
秋の横浜へ、どうぞ。
鶴見大学日本文学科